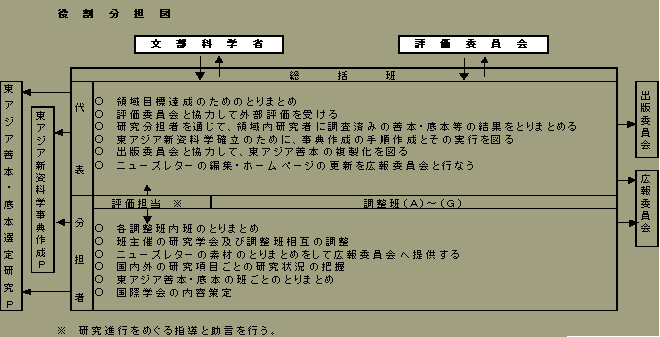|
【 本領域の内容と手順及び進行に伴う修訂 】
本特定領域研究には、出版印刷文化と社会をめぐる研究を円滑に遂行するために、1班の総括班を置き、領域全体の総括と研究の円滑な推進および研究結果の評価を行う。また、7研究項目を柱とする調整班を設け、調整班には40件の計画研究とそれを補完するための公募研究を立てる。同時に、研究全体を側面から学際的、国際的に援助するための研究推進・協力部門を設け、内外の研究者及び先行の特定領域研究の協力を仰ぐ。また本領域研究に対する評価及び指導を受けるために、独立した評価委員会を設ける。
ロ)評価委員会(4名)
ハ)総括班
ニ)広報委員会(3名)
ホ)出版委員会(3名)
ヘ)研究推進・協力部門(研究顧問・研究協力)
ト)特定領域運営事務局
チ)計画研究と公募研究との連関と役割分担
◆ ◆ ◆ 【 研究組織名簿 】
(1)領域代表者 :磯部 彰 東北大学東北アジア研究センター教授 (2)評価委員会委員:
(3)総括班(10名) (※事務局と調整班との関係を密接に保つため、必要に応じて事務担当者を調整班より起用することがある。)
(4)調整班代表者 調整班と計画研究(計画研究代表者 40名) 調整班とそれに所属する計画研究代表者をここに示す。調整班会議には、当該研究項目に関するすべての研究者が参加するものとする。(◎総括班 ○調整班代表) 《 調 整 班 》
《 研究推進・顧問、研究協力部門 》 国 内
《 公募班(28名)》
〔Ⅰ〕平成15年度、16年度共通の計画・方法
|
〔Ⅱ〕平成16年度
| ○ | 平成15年度の計画・方法を継続する(但し、評価委員会等の意見によっては、計画・方法に再検討を加える)。 |
| ○ | 平成15年度に設置した①東アジア善本底本プロジェクト②東アジア新文献学事典プロジェクトの継続をしつつ、そのとりまとめをして冊子体(稿本)とする。 |
| ○ | 評価委員会に最終報告をし、外部評価を受け、総括班全体で研究のとりまとめをする。 |